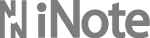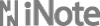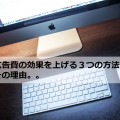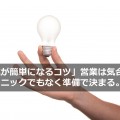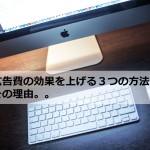これからの社長の仕事。40代中小企業の経営者がやるべき事。
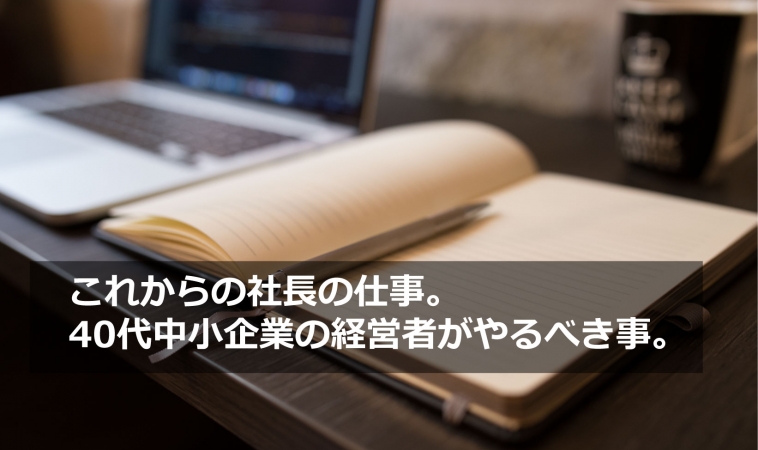
「これからの社長の仕事」このワードで、検索される方が多いようです。完全な私見になりますが、思うことを書いてみました。
これからの社長の仕事ということですが、社長の仕事は今も昔もこれからも、本当は変わらないのだと思います。
しかし、これからはどうすれば良いか?と今考える時点で、今まで社長の仕事ができてなかったのかもしれません。
では、そもそも社長の仕事とは何でしょうか?
ビジネスは、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」と言われていて、特に中小企業の経営者は、その事を中心に動いていいるのではないでしょうか?まさに、それが社長の仕事になっています。
ヒトを採用し教育し面倒をみる。モノを作ったり仕入れたり。カネの工面に走りまわり。会食やネットで情報を仕入れる。確かに、それぞれ会社にとってビジネスにとって重要な事です。
でも、それは社長の本当の仕事ではないと思うのですよ。
2000年代までは、それで良かったと思います。それだけでも、十分利益が出たと思います。また40代の経営者の多くは、そのような先輩の経営者を見て育ったことだと思います。
「社長になれば、いい思いが出来る!」と。でも、今はそれだけでは無理な時代です。これからも無理です。
では、その理由を考えて行きます。
そもそも社長とは何なんでしょうか?言い方は悪いですが社長が社長である価値とは何でしょうか?1度は考えたことある方もいると思います。
なぜ、社長が社長でいられるのでしょうか?
少し時代をさかのぼって1960~70年代。今の40代経営者の生まれた時代です。この時代は、ご存知のように高度経済成長の時代です。
日本経済が飛躍的に成長を遂げた時期は、1954年(昭和29年)12月から1973年(昭和48年)11月までの約19年間である。
これは、40代経営者の親世代が戦後のモノのない時代から、コツコツと積み上げてきた努力に、団塊ジュニアというベビーブームもあり、先進国では珍しい人口が大幅に増えたということ。そして、日本の技術の高さが海外でも評価されモノが売れたことなど、世界では例のないミナクルな事が重なって出来た訳です。
そして、10年後。1980年に入りバブル景気です。
バブル景気は、景気動向指数(CI)上は、1986年(昭和61年)12月から1991年(平成3年)2月[1]までの51か月間に、日本で起こった資産価格の上昇と好景気、およびそれに付随して起こった社会現象とされる。
このように、40代経営者が生まれてから高校を卒業するあたりまでは、ずっと景気はよかった訳です。そのような環境で育ったのです。
ということは、景気の良いときの経営をみてそだった訳です。それは、自身の周囲だけなく、当時のテレビドラマを見ても同じような舞台なのです。
「社長になれば、いい思いが出来る!」は、無意識にこの時に覚えた感覚はあるはずです。
「いつかはクラウン!」「いつかはベンツ!」「いつかは高級マンション!」の時代です。そのような事が、社長になるモチベーションだったのではないでしょうか?
話を戻して、では、なぜ当時の中小企業の社長は社長でいれたのでしょうか?戦後はモノがない時代です。当然モノを作れば、サービスをすれば儲かります。ニーズの宝庫です。考えなくてもニーズは見えているのです。サラリーマン時代までは個人事業主が多かったという事もその理由です。他人の元で他人の作った仕事をする理由がないからです。その後の経済成長期も同じで、ニーズがあるので、言葉は悪いですが、誰でも社長になれた訳で、利益もそこそこ簡単にだせたのです。当然、良い技術やサービスがあった事もありますが、見えているニーズに合わせれば良かったわけです。
ただ、この時はITはまだありません。社長が社長であった理由としては、情報なのだと思います。社長になる方法を知っていた。顧客を得る方法を知っていた。という差が社長と社員の違いで、なので社長の多くは、今のように経営の本音やビジネスの立ち上げ方を教えないヒトも多かったように思います。それが生命線だからです。
そして、2000年に入りIT時代に入ります。ITバブルという事もありました。
日本では、1999年(平成11年)1月から2000年(平成12年)11月までの景気拡張期を景気の名称(通称)で、ITバブルの他に、IT景気(アイティーけいき)や、ITブームなどと呼ばれる。
そこから、15年。様々な仕事がITに置き換わり、または情報の非対称性がなくなり、景気とは関係ないところでも淘汰されて行きました。これは、社長業という情報をもっているだけでは社長の価値がないと分かったという事です。
少し、ダメ社長ばかりみたいな事を書いてきましたが、少なからずあると思います。しかし、そのような社長ばかりでなく、戦後も好景気時にもIT時代にも素晴らしい社長もたくさんいる訳です。
その差は、何でしょうか?
時代の変化とともに、事業の中心は、一次産業から二次産業、そして三次産業へと移ってきました。
コーリン・クラークは、『経済的進歩の諸条件』(1941)において、産業を第一次産業、第二次産業、第三次産業に3分類し、経済発展につれて第一次産業から第二次産業、第三次産業へと産業がシフトしていくことを示した。これは17世紀にウィリアム・ペティが『政治算術』(1690)で述べた考え方を定式化したもので、両者にちなんで「ペティ=クラークの法則」と呼ばれる。
第一次産業 - 農業、林業、水産業など、狩猟、採集。 第二次産業 - 製造業、建設業など、工業生産、加工業。電気・ガス・水道業。 第三次産業 - 情報通信業、金融業、運輸業、小売業、サービス業など、非物質的な生産業、配分業。
今でこそ、大手企業といわれる企業や人気企業は、どこに分類されていますか?そこに答えがあると思います。
冒頭で書きましたが、「これからの社長の仕事ということですが、社長の仕事は今も昔もこれからも、本当は変わらないのだと思います。」
それは、今も昔も、社長の仕事とは「仕事を創ること」です。むしろ、それしかない。それがすべてだと思います。
「作る」ではなく、「創る」です。
営業や広告で仕事を作って忙しくすることではないのです。仕事を創造して、創っていくことが必要なわけです。
そこには、「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」は集まってきいます。極端な話、探しにいかなくても良いのです。
逆に、それを怠ることで多くの中小企業は10年以内に消滅してしまいます。こちらにその記事を書いています。
(関連記事:事業成長の法則。創業から7年目には次の事業を創ること。その理由とは)
スタートアップと呼ばれる、IPOやM&Aを目指す起業家の業界があります。そこでは、何か新しいことを創ることばかりにチャレンジしています。それ以外の20代の若い起業家も、新しい働き方を模索し創っていっています。アメリカでは、大手企業よりもNPOへの就職が人気であったりします。中東やアジアの起業家が非常に優秀だとも聞きます。その人たちは、新しいことにチャレンジし、失敗し、仕事を創っています。
40代、中小企業の経営者。これからの社長の仕事。
それは、ニーズを見出して「仕事を創る」その1点だと思います。
良い、仕事を創れば、良い人材もあつまり、人も育つものです。
(関連記事:成長する会社と消える会社の社長。)
アイノートでは、中小企業の事業成長のお手伝いを行っております。
コンサル+アウトソーシングで、柔軟にスピーディーに成長戦略への取組を実現します。
・3年後の事業成長をつくります。新規事業の立上げをサポート
http://inote.co.jp/new-business-consulting/
・WEBマーケティングをアウトソーシングで、コストを抑えて戦力アップ。
http://inote.co.jp/web-consulting/
・コンテンツマーケティングでブランド力の強化。
この記事がいいねと思ったら「シェア」お願いします。
↓