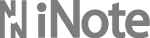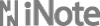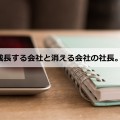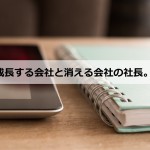経営ビジョンがない企業の成長は続かないその理由

お金が目的から、手段に変わる時がある。
ビジョンがない( 浅い )時には、目先のお金が目標になってしまう。
すると賛同者は増えないので、事業が長期的に成長するは難しくなります。ある時にお金が目的から手段へと変わる時があります。そこから企業は成長するのではないでしょうか?
起業の動機としても、稼ぐというものが大きいことは否定はしません。それは純粋な動機だと思います。
しかし、その動機だけでは企業は成長できません。
なぜなら、お金を稼ぐが目的なので、自分のモチベーションの持続や、従業員や取引先に無償の賛同を得れることがないからです。
私が、過去の経営で失敗したと思う1つに、この「ビジョン」というものがあります。
創業時には、お金が動機でした。会社は利益をあげる事が大切です。
しかし、その先に明確なビジョンがないと、ただ稼ぐだけの企業になり、そこから価値のあるアイデアや事業も生まれにくくなります。
何かを判断する基準がお金基準になってしまいます。それではお客さまや従業員から真の賛同は得られることはない。
いくら稼ぐ。これは大切な指標ではありますが、KGI(ゴール)でなく、KPI(過程)だと思います。
お金をただ稼ぐというだけでは、手段を問わなければ、なんなりと達成できてしまいます。
ただその場合、そのステージから(金額)次のステージへの発展は難しくなる。大きな壁が現れる。
動機が内(自分の利益)に向いているものに、無条件で賛同してくてる人は、いないからです。
誰が貴方の欲求を満たすためだけに、協力してくるのでしょうか?価値とお金はトレードです。
多くの企業や経営は、この壁にあたり。越えれずにいるのではないでしょうか?
一方、お金がその先にあるビジョンという目標を達成するための手段となると、その壁は気になりません。
なぜなら、利益を上げて再投資し、ビジョンに向けて価値を上げていくので、そのビジョンに賛同する人は、意外と多いからです。
賛同する人とは、お客さまそのものです。資本家も従業員も取引先も賛同者です。
それは、人はお金よりも、自分の人生の時間というものが重要だと気づく時があり、自分が生きている意味や価値を考えだすからです。
長期的に見ると、どんなテクニックや学問よりも重要なものがビジョンと思います。
お金が目的であっても、一定数のお客さまに買って頂くことはできてしまいます。一定数の人には従業員になってくれる人もいます。
ただ、それは企業が提供しているものとは違うことに価値を感じているケースが多いのではないかと思う。
それも大切なことでしょうが、本質ではないので、一定数以上は増えないようになります。
ビジョンがなく、賛同者が少なくなり、成長に陰りが見えると考えるパターンとして、賛同はしていないが、なんとなくお金を出す人や集まりを探します。
言葉は悪いが、情弱、リテラシーが低い、旧態依然で変化が少なく、ビジョンもなく劣化したスキルや知識でも対峙できる市場を探します。
そこでしかお金をもらうことが出来なくなるからです。当然、その先には三方よしどころか、二方にもメリットあるかも微妙な未来です。
なぜなら、その集まりの中だけで活動することは、ある意味鎖国状態であり、社会や時代の変化との差が広がり、よってお客さまのニーズとも差ができる。
そして価値そのものが低くなる。そんな循環になるからです。
では、ビジョンとは何か?ビジョンは大きければ大きいほどよいと考えます。またビジョンは個人的な内容であってはなりません。また、どこかのコピーや他人の借り物であっても意味はありません。
経営ビジョンとは何か?
経営ビジョンとは、『長期的時間軸を持って、企業の目的や使命、実現・提供すべき企業価値などの「将来あるべき姿」を明らかにしたもの
引用:weblio
ビジネスの基本を辿れば、社会の課題の解決と、その根底にある人間の欲求を満たすことです。それしかありません。
そのビジョンである社会の課題や人間の欲求を満たすサービスや仕組み、モノ、それを提供する行為がビジネスであり、その組織が企業です。
それを達成するための、道具の一つがお金です。一番汎用性が高いくて便利なのですが、お金そのものにはあまり価値がありません。お金と交換できるものに価値があるのです。
料理に例えるなら、ビジョンは料理であり、お金は包丁や鍋です。スキルや人は素材です。調理人が経営者です。
言うまでもなく、素材がもっとも大切です。道具も必要です。しかし何を作るのか?という完成する料理のイメージ次第で、美味しくも不味くもなります。
お金が目的とは、包丁や鍋を手に入れることに懸命になっているという事で、よい包丁や包丁を数多く手に入れると、最高の料理が作れると思ってしまったり、また目的が包丁コレクターのようになってしまいます。
お腹を空かせた、お客さまが、包丁コレクターの元に行くのでしょうか?包丁ばかり多くあるところには、包丁を借りくる人ばかりが集まります。
お金目的の人しか集まらないとは、このような状態です。
お客さまが欲しいのは、料理です。料理を食べたいのです。
ただその料理にも、いろいろあります。それは和食やイタリアンといった差ではなく、その料理を通して何を提供するのか?という点での差です。
単に空腹を満たすものか?健康にズームしているのか?心に感動があるのか?など、それを食べたあとの満足感や欲求を満たす。またそれが社会や生活に何か変化を与えることが、料理の価値の本質です。
そのように、ビジョンとは、企業の活動を通して、社会や生活にどんな変化を与えるのか?それにより何かが豊かになるもので、なくてはなりません。
それで社会に生活に人にの課題を解決し豊かさの提供の先に、どんな未来を創るのか?というところまで深く掘下げて理解しておくことが大切だと考えます。
お金が目的から、手段に変わる時がある。
これは、人によってタイミングはそれぞれだと思います。
私の場合は、新しい事業をつくるために活動し、何が成功するのか?を学んでいる中で、気付きました。
自分が成功することを探しても、見つからないということを。
このあたりに気づくと、お金は目的から手段と意識は変わっていきます。そうなると、10年というサイクルで見た場合には成長します。
それには理由があり、前述の賛同者という、自分の外だけでなく、モチベーションという自分の中にも変化が起こります。
このモチベーションの変化は凄く大切で、上がる、続くという変化が起きます。
お金を目的から手段へと変えるには、勇気も入ります。リスクもあります。短期的には損をします。
目先の利益を追わなくなるので、収入はへります。私自身もみるみる貯蓄はなくなりました。
しかし、それは一時的なもので、長くとも2〜3年までだと思います。
気づいてのメリットで大きなことは、損得だけで物事を判断しないようになり、自由な選択ができるようになったこと。
仕事をする期間を20〜60歳の40年間と考えてみると、
お金を目的にして、目先の利益にとらわれて、不本意ながらも、ずっとそれを追うのもよし。
お金は手段と考えて、大きなビジョンを追いかけるもよし。
その選択によって、達成できることは変わってくると思います。