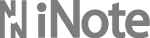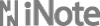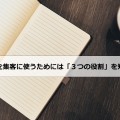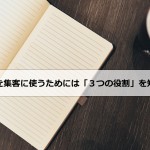コンサルタントとは?どんな使い方と選び方がよいのか?
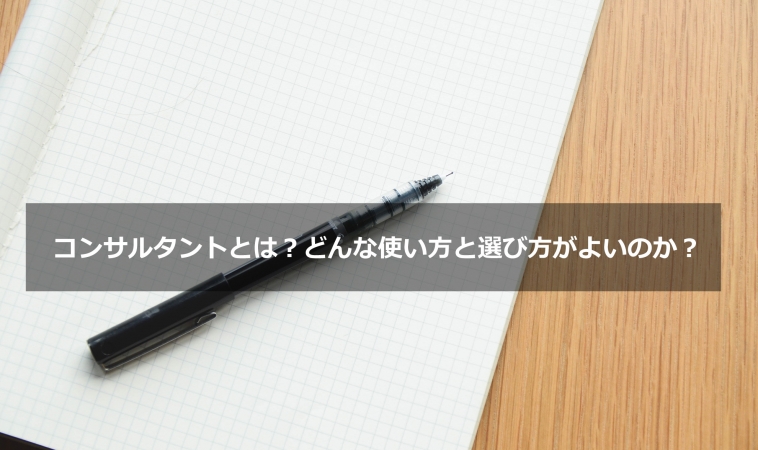
私も、20数年間は事業会社にいて、コンサルタントをお願いする立場にいました。
その目線からと、今、自身がコンサルタントとしての目線でみて
コンサルタントを使うときのメリットとは、何だろう?を考えてみました。
多くの場合は、専門的なノウハウやスキルを求めると思います。
当然、それは必要で、それは「学問」「経験」「考え方」といったバックボーンとなる部分と
具体的に課題を解決にもっていく実践的な「スキル」「技術」といった2つのものから成るものです。
前者は、クライアントの考え方を変えるもので、知的財産として残ります。
後者は、目先の課題を解決することに役立ちます。
言い換えると、前者はいわゆる「先生コンサルタント」で、後者は「スキルの外注・アウトソーシング」です。
これを、ひとくくりにしてコンサルタントを依頼すると、希望していたことと、提供するもののアンマッチが起こります。
お客さま目線では、話はわかるが、実際に実行することが難しい。や
コンサルタント目線では、お客さまが実行しないから変わらない。といった話は、
このアンマッチから起こるものでは、ないかと思っています。
知識が欲しいのか、スキルの外注なのか?
知識だけを提供するのか?スキルで解決するのか?
互いにマッチングの理解が重要だと考えます。
また、今後は前者の知識のみで、実践経験をともなわないと衰退すると考えています。
なぜなら、情報社会では教科書にあるような専門知識は、誰でも簡単にてに入るからです。
必要なのは、その知識で実践しての経験です。
しかし、それはクライアントの現状、業種、地域、お客さま、時代によって
すべて結果は異なるので、これをすれば正解!という王道はないと思っています。
では、どうすべきか?というと「知識」と「外注」のハイブリッド型です。これが今は一番よいのではないかと考えています。
ただし、これは双方にリスクも発生します。
コンサルタントは「教える」で完結していたものが
自分が言ったことを自分でするので、結果が出ない時のリスクは相当高くなります。
本来は、これがあるべき姿なのかもしれませんが逃げ場はなくなります。
考え方を出来ない理由をクライアントに探すのではなくて、出来る方法を市場で探すへ切り替えが必要です。
一方、クライアントは、結果がもろにでるので、それを受け入れる精神的な負担リスクが生じます。
コンサルタントが行っても結果がでないということは、問題の本質がそこではなかったという事になります。
そこで、本題に入りますが、ではコンサルタントを使うメリットとは何でしょうか?
まず1つは、第三者目線。
これは、私がスタートアップベンチャーで学んだことですが、成長ビジネスを創るには
業界の固定概念、旧態依然、既得権益といった視座に考え方が支配されていると、生まれない。
なぜなら、そこを基準として掘り下げても、その土壌がだめな場合は、そこをいくら掘っても
そこには資源がないからです。
スタートアップベンチャーの人たちは、若いひとが多く、いい意味で業界の経験や社会経験が少ないので
既存の常識にとらわれない。(逆にその甘さもありますが・・)
ですので、既存業界の知識を深くもっている企業や経営者と、第三者目線が加われば、強いものが生まれるのではと思っています。
2つめは、専門知識をもった外注。
これは、今までだと「作る」「売る」「考える」など縦割り的なサービスが多いと思いますが
今後は、その垣根というものは、なくなります。
製造業がサービス業も兼ね、IT企業が自動車を作り、販売会社が作業もするといったことが
時代の流れだからです。
例えば、WEB制作会社が作るだけでは成り立ちません。コンサルタントも教えるだけでは成り立ちません。
企業の組織でも、よくあることですが、仕事を分業しすぎると、部署間の責任のなすりつけ合いが起こります。
これによって、達成できるはずのミッションが達成できない。といいた事は日常的に水面下では起こっていると思います。
ですので、コンサルタントも実務を請負うということは自然な流れです。
それぞれ、考え方はあるとは思いますが、大まかなメリットとしては、
以上のような目的での使い方が、クライアントにとってもコンサルタントにとってもよい方向なのかなと考えております。
企業の採用は、恋愛と同じと言われるように、外注やコンサルタントも同じで、双方が望むことと、提供することとの、マッチングが大切です。
知識を得て、自分でできるようになりたいのか?
スキルがないから、誰かにかわりにやってもらいたいのか?
これを理解して、コンサルタントはサービスを提供しないとアンマッチが起こると思います。