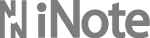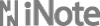地方創生に必要なこと。地方の活性化を阻むITと情報伝達の壁

地方創生には、まずシンプルに簡単なところからすることが大切だと思います。
地方創生に、国や自治体、大手企業など様々な動きがありますが、個人的にはそれよりももっと前にすべき簡単なことがあるように思う。
たとえは良くないかもしれませんが、大掛かりな空中戦よりも、地道な地上戦です。
そもそも、地方創生の主役はだれかというと、当然、地方に住んでいる人です。その中でも、キーとなるのは地方の企業や店舗、生産者だと思う。
著者個人的にも、実家は関西の地方で、実家に戻った時に感じる格差。また、前回の起業時も大阪で、その後、東京にでて来た時に感じた情報と意識の格差。
それから、数年たったいま感じる格差。
その経験から何が必要か?何からすべきかを、地方に住む人(情報の受け手)、地方の事業者(情報の発信者)、都心の企業や国・自治体(火つけ役)の3者の視点で考えてみました。
■問題は、未だに情報の格差がある。
地方との情報の格差は、以前にくらべると少なくはなってきているとは思いますが、まだまだ格差はあります。
まずは、情報の受け手(地方に住む人)の話から。
これは、客観的にみても情報の受け手が、それを得る手段を活用していない。分かりやすい例が、facebookなどのソーシャル・メディアです。
年代にもよりますが30代半ば以降の方であれば実感はあると思いますが、自分の同級生を検索してみて下さい。検索結果に出ますか?私の場合は20才くらいまでで地方在住の方を検索しても、出てくるのはたったの5%ほどです。
facebookの利用者数は、2014年で2400万人とあります。高齢者と子供を除いた対象者が1億人と考えても、4人に一人は使っているという話です。
しかし、実際に地方の知人、友人を検索した結果からみると、その多くは都心に偏っていることは想像できます。
それは、ソーシャルメディアのように無造作に流れてくる情報は、いまだに地方には届いている数が圧倒的に少ないということです。
参考データ:ソーシャルメディアのデータまとめ一覧。
では、無造作に流れてくる情報がなければ、自らgoogleなどの検索エンジンから情報をとりにいっているのでしょうか?それも、そうではなさそうです。
これは、サンプルがすくないのですが、自身が管理する複数のサイトのgoogleアナリティクスの解析結果からみる限りでは、人口差はあるにせよ、圧倒的に関東一極化です。以前に運営していた美容ポータルサイトでも同様の傾向がありました。
では、スマホのアプリという角度からの情報はどうでしょうか?スマホでのインターネット利用率でも、最高値は東京都の55.3%、最低値は鳥取県の37.1%。東京と地方とでは1.5倍ほどの格差があります。
また、全国でトップの東京は55.3%で、10位の広島県では46.7%。トップ10位内でも10%近くの差があることになります。
では、何から情報を得ているのでしょうか?テレビです。地方はテレビが主な情報源になっています。
情報も受け手という視点からみてみると、このような格差が未だにあるわけです。
この環境で、いくらインターネットで地方創生関連の情報を配信したところで、肝心の地方には届いていないということです。そうなると当然、意識の変化も生まれにくい。
一方、東京ではスタートアップやIT大手企業を中心に、新しいサービスは、どんどん生まれてきています。新しいサービスに日々触れている人とそうでない人、情報を日々受けている人、いない人。
皮肉なことに発信すればするほど、この意識差は日々広がって行っているのです。受けて欲しい受け手が受けていないから。
では、なぜこうのようなことになっているかを次に考えていきます。
■地方の事業者こそITの最先端を行くべき
なぜ、地方はインターネットからの情報収集をしない(少ない)のか?
それは、情報の発信者(地方の事業者)に問題があると思っています。私が実家に戻った時に、東京と同じようにスマホから地元の店舗やレジャー施設を検索すると、ほぼ情報がない。
これが現実です。あったとしても、10年前の電話帳レベルの更新されていないホームページや、スマホ対応していないところが多数です。これは、もう次は見ませんよね。普通なら。
しかし、これに気をとめている事業者は少ない。
私がゴルフ場のWEBマーケティングの仕事に関わっていたときも、同様に感じました。2015年前半のデータですが、ゴルフ場のホームページのスマホ対応率は約10%ほど。
1ユーザーとして、ゴルフ場を予約する際にも、スマホ対応ではないことと、ホームページの構造の問題で、予約システムまでたどり着きにくい。そうなると、利便性のよいGDOや楽天goraなどのゴルフポータルを使うことになります。
これは、ゴルフ場としても、予約毎に手数料がかかるのでデメリットではないかと思います。そのコストを自社のホームページや、ゴルフ場や地元の店舗との連携などのサービスに使うことのほうが地方創生にはよいのではないでしょうか?
また、情報としてもゴルファーが欲しい情報をだすことです。
たとえば、当日の天気。これもホームページに天気情報はあるわけですが、一歩すすんでリアルタイムで動画を配信することもできます。
こちらのsafieというカメラですが、これは防水で屋外にも設置できます。動画もライブでスマホに配信もできるので、これでゴルフ場のリアルタイムを流すことで天気をしることができます。
カメラも超広角で170°映ります。この事例としては、ある観光地が、桜の時期にこれで開花の進捗を配信して喜ばれているそうです。
一方、東京で日々使っているWEBサービスにアクセスしたところ、地方の情報は少ない。見ている分には東京と同じですが、そこにある情報を使うことができない。実際にアクションすることがないのです。
これらも、ポータルを運営していた経験からすると、WEBサービスの運営側が情報収集するときに、googleなどの検索エンジンで地方の情報がみつかりにくいということがあります。よって地方の情報は少なくなる。
それは、地方の事業者が情報を発信していないからです。なかなか現地まで、情報を探しに行くことはできませんから。
次に、インバウンド(訪日外国人観光客)。
これも、地方創生の役割として非常にチャンスがあります。様々な記事や専門家の方が語られているので、詳細はそちらにお任せしますが、ここへの取組も遅れているように感じます。
ここでも、やはり大切なことは、まず情報発信です。この場合は、自社のホームページの外国語対応といったこともありますが、海外からの観光客の方は日本のWEBサービスはあまり使わないそうです。
これは我々が、逆に海外へ行った時に現地のWEBサービスにアクセスしますか?ということです。なかなかしませんよね。
ですので、この場合は海外からの観光客の方なので、トリップアドバイザーなどのグローバルな観光サイトに情報をだすことになります。
そうなると当然、店舗や施設の現地での外国語対応は必要ですが、英語が話せなくとも、せめて英語での翻訳メニューやナビゲーションくらいは用意しましょう。
これくらいは、クラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングを使えば、ほとんどコストをかけずに出来るはずです。
これらのクラウドソースングも、現状では、東京の企業から地方のフリーランスといった方向の仕事の流れが多いようですが、逆ももっと活用したほうが事業の選択肢は広がるはずです。
今の時代のビジネスの勝ち方としての常套手段は、「情報を出す」。
これが基本です。情報をだすところに情報はあつまり、情報があるところに人は集まる。
いたってシンプルなことですが、これを行っているのは都心と地方の一部の意識が高い人たちです。
ニュースでも見る「地方創生は人を動かすこと」とありますが、大きな仕組みの話よりも、まず人を動かすには情報を出すということが絶対条件ではないでしょうか?
これまで、インターネットでの情報配信に目を向けてきましたが、今度は違う角度からみてみます。
人手不足。人材不足。これも地方の事業者にとってはおおきな問題だとおもいます。ビジネスの面からみると、人がいないから事業展開ができない。これも、よく耳にする話です。
でも、それは本当でしょうか?
以前の記事でも、近いことは書きましたが、地方こそITを活用して人材を使わなくとも拡大できるビジネスを考えることが大切です。前述のクラウドソーシングや、外部のコンサルティングなどのアウトソーシングの活用。
また、人力でなく機械化、コンピュータ化による自動化です。今ではIoT(モノのインターネット)やロボットの技術は進歩して、製造業以外でも、つかえそうなものは多くあります。
話は人材からそれますが、この自動化は地方創生に非常にパワフルな技術だと考えています。
なぜなら、このIoTやロボットを使うことで、日々の作業から様々なデータがとれるからです。このデータは自社の作業に活かすだけでなく、大手企業の持つビッグデータと共有することで、新たなビジネスに繋がる可能性はあります。
先日、参加したIoTの勉強会でもキリンのデジタルマーケティングの方の経験からの話にもありましたが、データは自社だけで使うとうまくいなない。他社と共有することが大切だとおっしゃっていました。
このIoTという領域は、まだ大手企業も取り組んでいるところは少ないそうです。政府での会議に参加しているのSap japanの話によると日本は、まだIoTによって様々なビジネスが変わるという意識が低いという感想です。
これは、逆に考えるとチャンスではないでしょうか?大手が取り組んだあとから参入するのか、先んじてノウハウを貯めるのか。これは雲泥の差があることはわかることです。
人材に話をもどすと、人がいないから出来ないといった思考を、人を使わなくても出来ることに、変えて考えてみる必要はありそうです。
■有益な情報や手段よりも違うものが先に届いている現状
次は、情報の火付け役(都心の企業や国・自治体)の視点から見ていきます。
どうすれば、地方の事業者のIT化を促進できるか?といったことは都心の企業にかかっていると思います。これには営業のコストや売上単価など、様々事情はあるとは思いますが、まず地方に新しいサービスが普及するのが遅い。
これは、私が大阪で起業したときの実感値ですが、3年位の時差はあるのではないでしょうか?
グローバルに見ると、シリコンバレー→3年後→東京→3年後→地方といったような時差でしょうか。そう考えると最低でも、6年は遅れて浸透するということになります。これは、前述のfacebookの利用率などにも反映しているかと思います。
ただ、遅れてでも浸透すれば良い方で、多くは東京どまりです。今では、地方でもスタートアップは出だしてきているようですが、私自身もその言葉は東京にきてから知りました。WEBサービスを運営していた当人でもそれくらいなのです。
それには、多くのサービスが東京圏内だけでもビジネスが成り立ってしまうということがあるのだと思います。よって良いサービスでも、存在すらしらない地方に住む人は多い。これが実感です。
これが、知らない。するものがない。サービスを使わない。インターネットから情報を収集しない。といったことに繋がっています。
では、全く地方へのアクションがないのか?といえば、そうでもありません。
情報や知識の少ない、所謂、情報弱者をターゲットとした業者は、逆に東京よりも多いのかもしれません。正確にいうと、都心では売れないものを、都心より競合も少ない、情報に弱い地方へ営業をかけている業者が多いことも事実です。
主なものとしては、情報ビジネスであったり、最近は少ないのかもしれませんが、高額リースのホームページや防犯カメラなどのあまり価格と価値が見合わないように見えるものは、地方では売れるそうです。
このように地方では、有益な最新のITや、利便性の高いサービスが浸透するまでに、このようなものが浸透するといたことがあります。
こうなると、高額リース→利用者は少ない→効果がみえない→ITは無用、といった偏った認識になってしまう。これも原因として多少なり、あると思います。よって、インターネットでの情報発信もしなくなる。情報がないから使わないといった悪循環にハマるのです。
スタートアップやベンチャーも課題はあるとは思いますが、地方への活動をひろげることは、長い目でみるとメリットはあると思います。
また、国や自治体も有益なサービスを地方に浸透させることに補助金などをだすといったことも有効な手段かもしれません。その有益なサービスかどうかの判断は難しいですが。
そのうえで、情報の流通がスムーズになったところに、適切な情報を配信する。そして地方に届けるといった地道なことが大切かと思っています。
■まとめ
インターネットやIT、情報メディアといった話に偏りましたが、地方創生の土台としては非常に大切なだと思います。
- 都心の企業は、地方へもサービスを届けること。
- 地方の事業者こそITを活用すること。
- 情報を発信すること。
- それによりインターネット利用率の格差をなくすこと。
しかし、この地味ながら、あるいみ簡単でシンプルなことができていない。地方の事業者とのかかわりや、自身の経験からそう思います。
この積み重ねが、意外と大きいのではないかと感じています。